最近、毎日シコシコ 色えんぴつをナイフで削っています。
色えんぴつをナイフで削っています。
ミニ鉛筆削りだとすぐ芯が折れちゃう。そうでなくっても、力いっぱいぐりぐり色をぬるのでボキボキ折れるし。
ぐりぐりボキボキするのはわたしではなくって、お子さん、クライアントさんです。こども向けのセラピーに使っているのです。
大人はことばで表現してスッキリするところがあるけれど、こどもの場合、「どんな気持ち?」と聞いても、「え〜・・・わかんない」と言われるか、黙られてしまいます。
そこで「絵」で表現するアートセラピー登場。
とってもかんたん、そして効果ばつぐん!誰にでも使えます。やり方はこんなふう・・・。
もともと潜在意識の中は言語というよりもイメージ優勢の世界なので、ダイレクトに絵と色で表現してもらうことによりネガティブな感情や信念の解放を促すことができます。
そういえば、昨晩NHKの番組で企画案などを絵で表現しているという会社が紹介されていました。自分の考えを一枚の絵にしてみると、文字を並べるよりも広がりのある表現ができ、自分でも新しい気づきを得ることができるということでした。
お子さんはたいてい親に連れられてセラピーにきた、という意識が強く、「自分が修正されなければならない」ことに不満を抱いています(ほんとうは修正ではなくて、視点の転換なのですが...)。セラピストは親とグルになっている敵にされます。
そういう場合はノーテンキに、「○○ちゃ〜ん、一緒にお絵描きしよ〜♪」と誘ってみます。すると、「え〜、下手だから・・・」と言いつつもたいてい嬉しそうにのってくれます。
「ねぇねぇ、○○ちゃん、学校ちょっとお休みしてるんだって?行けない日って、身体にどんな感じがあるの?」と遊びにかこつけて、すかさず身体の感覚から尋ねてみます。
すると、「う〜ん、ここんとこ(胸と喉をさして)になにかある感じ」というお答え。「あそう、それってどんなものでできてるの?」とさらに身体の中の感覚の大きさ、重さ、硬さ、色、質感、密度などを尋ねます。
身体の中の「それ」をよ〜く感じてもらいながら特定したら、「じゃあさ〜、それ、そっくり紙の上に移してみてよ。紙の上にお引っ越しだよ。色鉛筆で描くとどうなる?」とうながすと、まったく躊躇なく描きすすめてくれます。
たまたま紫色が折れてたら、「どうしても紫じゃなくっちゃダメなの」と言われ、あせって削るわたし。削って渡すと、ぐりぐり力いっぱい塗っているうちにポキっ!また、あせってわたしが削っていると、「折れた芯で描くよ」と、ちっちゃい芯で必死に描いています。(ちゃんと自分の気持ちの色は決まっていて、それは絶対ゆずれないのです。それにこの力の入れようからも、紫のエネルギーのパワーが伝わります。)
描きあがったらちょっと絵の説明をしてもらいます。びっくりすることに、ひとつひとつにちゃんとした細かい意味があのです。自分の気持ちの細部までを表現しています。(この説明で何が起きているのかは、だいたいつかめます。)
つぎに、わたしが絵のメインの部分にマイクを向ける仕草をして、絵にインタビューして語ってもらうのです。
「ねえねえ、この人(絵のある部分)、何て言ってる?何困ってるの?」「どうして欲しいのかな?」と絵にマイクを向けると、○○ちゃんが絵になりきって答えてくれます。そうなのです、自分のことじゃないと、あんがいすらすら正直な気持ちを語ってくれます。(「絵」じゃなくって、ぬいぐるみを使うこともあります。つまり、こどもと同じ悩みを持っているぬいぐるみにインタビューするのです。)
そして本人である○○ちゃんに、この困っている人(絵のある部分)に対してアドバイスしてもらいます。「ねえねえ、○○ちゃん、この人、こうこうこうで学校行けないだって。どうしてあげたらいいと思う?」って。すると、本当は自分がして欲しいこと、あるいはして欲しくても気づかなかったことを語りはじめます。
自分のことだと気持ちも解決方法も思いつかないけれど、あんがい他人のことだとわかるものです。これは大人でも同じですね。ちゃんと解決策は自分の中にあるのです。
おおかた解決方法を語ってもらったら、「じゃあさ〜、その解決策使って、さっきの問題が解決したらさ〜、この絵はどんなふうに変わるんだろ?」
そして、もう一枚新たに描いてもらいます。さっきまで紫、黒、茶色のオンパレードだったのに、今度はピンクや水色、黄色などのラブリーで暖かい世界が描きだされます。
わお!自分で提案した解決策でここまで明るく自由になれるんだ!とびっくりします。
描き終わる頃には、本人も気持ちが軽くなっています。
もちろん、これはたんに描いて気分転換になるだけじゃなくって、無意識のうちに潜在意識の中の怖れを解放することに役立っているし、また心の方向転換を自然なかたちで行っているのです。
これは、別にお子ちゃま向けのセラピーでもなんでもなくって、大人にもとっても有効。わたしもお絵描き大好きなので、たまにやっています。
みなさまも、「な〜んかもやもやするなぁ」「なんだか、やる気でないよ」という原因がはっきりしない落ち込みや、「あの上司、あったまにきた!」なんていうように感情が高ぶっているときなどに、是非、気軽に紙を用意して、ぐりぐりと表現してみてくださいね。
うまく描く必要はありません。ただ描きたいままに。楽しくって簡単だけど、すっきり感、かなりありますよ〜。

 昨日はひさびさに熱海出張。
昨日はひさびさに熱海出張。





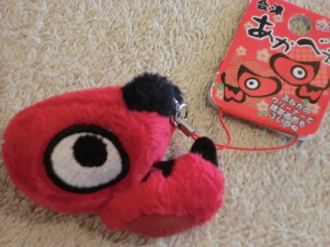



 セラピーCDなど販売中
セラピーCDなど販売中