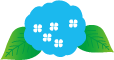
最近いくつか寄せられたご相談は、「学校を休みがちなこどもと、そのことに関してギクシャクする夫と妻」という問題。
ハイ、最近よく耳にする状況ですね。
ここには二つの問題があります。
「学校に行かないこどもをどのように扱ったらいいのか」ということと、「夫婦でのこどもに対する考え方、接し方に違いがあり、混乱が生じる」ということ。
親は自分のこどもが学校に行けないと、なんとかしてテコでも「行かせる」ことに苦心します。なぜなら、「学校に行けないこども=問題児」という考えがあるからです。(しかし学校システムを冷静にながめてみると、かなり不思議なトコロですよ〜、学校って。一日中同じ方向を向いてちんまりとハコの中に坐らされ、みんなまったく同じことをするよう強制され、同じようにできると「いい子」と褒め讃えられ、しないと「わるい子」のレッテルを貼られる・・・かなり奇妙なトコロです。みんなよくぞ卒業したな〜とも思えてきます。)
しかし、「学校に行かない」ことをもうちょっと引きの目線でみてみると、実際「いいこと」でも「わるいこと」でもなくって、ただシンプルに「行かないのだ」という事実があるだけなのです。もしも、そこに特別な意味あいがあるように感じられるならば、おそらくそれは親の書いた「こどもの筋書き(脚本)」にどれだけあっているか、はずれているかによる査定にすぎません。「みんながやっていることをできない子」=「欠陥がある子」というレッテルをはってしまっているのかもしれません。
しかし、ちゃんと学校に行けたからといって、すごい人になるわけでもありません。有名な話しですが、エジソンもアインシュタインもめちゃくちゃ変わったこどもで、どちらかというと問題児だったそうな。
だからと言って「学校に行かない」こどもをほっておきなさい、ということとは違うのです。まず、それが「いいことだ」「わるいことだ」という裁きの目線をストップさせる必要があります。なぜなら、こどもは「裁かれている」「親の筋書きにどれだけあっているかで自分の価値を測られる」と感じるのがいちばんつらいからです。
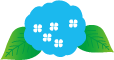
「いい」とか「わるい」を手放したときに、こどもは本当に安心して自分のココロを見せることができるようになります。そうですよね。「さあ、あなたのココロをみせてごらんなさい。わたしがすぐに「いい」か「わるい」か言ってあげるから」・・・なんて態度だったら、何も正直に話すこともできません。
こどもは感じているのです。親が勝手に「自分に対する理想の筋書き」を作っていて、それに沿って歩むべきだとあたりまえに信じている、ということを。「何も期待していない」と言いつつも、その筋書きからはみ出そうものなら、「とり乱す」「見捨てるわよ!というそぶりを見せる」「悲しんでいるところを見せる」など、あらゆる手を使ってこどもに罪悪感を持たせ、そこからはずれることをちょっとも許さないのです。
学校の友人との軋轢に悩んでいたり、うまく結果が出せないあれこれについて悩んでいるこどもにとって、「あ〜だ」「こ〜だ」の大人目線のアドバイスは何の癒しにも解決にもなりません。
自分がこどもの頃、落ち込んでいたときのことを思い出してみてください。「ちゃんとする」「筋書きに沿って生きる」ことだけを気にしている親の対応に「全然、わかってない」と思ったことがあるはずです。おそらくその時に欲しかったのは、「そのまま」の自分を受けとめて、包み込んでくれる安心感。すぐに立ち直る自分を期待してアドバイスやら手を貸されるよりは、何が起っているのかがわからなくってもただ受けとめて欲しかったはずです。
ただ無条件に、何が起っていようとも、その人の存在にOKを出してくれる、受けとめてくれる、どんな状態であろうと味方でいてくれる、そんな存在が一人でもいてくれると、わたしたちは心の中から前向きなエネルギーがわき出してきて、「よし!また頑張るか!」と前を向く気持ちになれるのです。
そうお話しすると、「え?だったら、こどもにやってますよ」とおっしゃる親御さんが多いことも事実です。
本当に「その子のため」のサポートするとは、どういうことなのでしょうか?
(その2へつづく)
(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/心理療法家・ヒプノセラピスト)
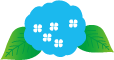

 集まったインターネットカフェは、B1にあってとってもアンダーグラウンドな雰囲気。トリ目のわたしにはコケそうなぐらい真っ暗で、なぜかこの時代にミラーボールまで回っているという。
集まったインターネットカフェは、B1にあってとってもアンダーグラウンドな雰囲気。トリ目のわたしにはコケそうなぐらい真っ暗で、なぜかこの時代にミラーボールまで回っているという。 本日はサイトのシステム変更なのでわたしの出る幕もなく(というか、もれなく毎回出る幕はありましぇん)、なので隣に鎮座し、頑張る二人を味わい愛でておりました(決して、邪気は送っていませんっ!)。
本日はサイトのシステム変更なのでわたしの出る幕もなく(というか、もれなく毎回出る幕はありましぇん)、なので隣に鎮座し、頑張る二人を味わい愛でておりました(決して、邪気は送っていませんっ!)。







 ここしばらく、騒音に悩まされておりました。
ここしばらく、騒音に悩まされておりました。 戻ってみたら、ちゃんと「音」はやんでいましたよ。
戻ってみたら、ちゃんと「音」はやんでいましたよ。




 中身は、夏にぴったりのレースをあしらった生成りのコットンバッグ、そして今までトライしたことのないようなハーフパンツ(おお、今でもオシャレ鍛えてくれます)。そして、美しいボトルのフレグランス(最近、まったく香りをつけてなかったので、これを機にまたトライします)。
中身は、夏にぴったりのレースをあしらった生成りのコットンバッグ、そして今までトライしたことのないようなハーフパンツ(おお、今でもオシャレ鍛えてくれます)。そして、美しいボトルのフレグランス(最近、まったく香りをつけてなかったので、これを機にまたトライします)。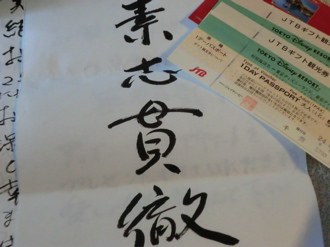


 セラピーCDなど販売中
セラピーCDなど販売中